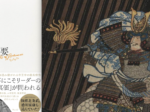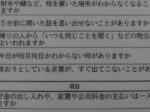忠臣蔵と『武士道』の話
- 2024/12/14
- できる人研究所, 仕事ができる人の歴史入門, 古典のすすめ, 夏川現代語訳古典, 武士道

12月14日は、「忠臣蔵」の日。
赤穂浪士の吉良邸、討ち入りがあった日ですね。
321年前のこと。
(新暦では1月30日)
それにちなんで、
泉岳寺では「義士祭」が行なわれます。
画像は泉岳寺にある義士たちの墓所ですね。
大石内蔵助も含め、
浅野内匠頭の墓とともに、彼らは一同、
ここに眠っています。
当時から物議を醸し出していた
四十七士の仇討ちですが、
新渡戸稲造さんの『武士道』には、
こうあります。
「復讐が正当と見なされたのは、
目上の者や恩のある者に対する信義が
断ち切られたときのみ。
自分自身が受けた危害や、
妻や子が受けた危害に対しては、
それを我慢し、許すべきとされたのです」
物語とは裏腹に、実際はかなり傲慢な
人物だったらしい浅野長矩。
それが江戸城本丸で刀を抜いたのだから、
許されるものではありません。
けれども、ただでさえ、
藩のリストラを推進している江戸幕府に対し、
部下たちが赤穂の藩を守るには、
お殿様の名誉回復をする以外になかったわけです。
そこで武士に名誉を汚された恨みを
部下が晴らすという理屈になりました。
実際は「殿ご乱心」だったとしても、
部下は「主君が正しい」という理屈で動くしかない。
実際、その行動が江戸の民に支持されたから、
四十七士は処罰を受けて
自害することになりますが、
藩は存続を許されることになったんですね。
すでに戦う存在ではなくなっていた
江戸の武士たち。
なのに支配階級には、ずっとい続けている。
そんな疑問に対し、
赤穂浪士たちは、命懸けで主君に支えている
「武士道の有様」を見せつけたわけです。
そんな文化がある藩を取り潰したら、
幕府への忠誠心も傾きかねない。
四十七士の命をかけた行動は、
結果的には実を結びました。
そんな時代でなくてよかったな……と
現代の私たちは喜ぶべきでしょうが、
誰のために、何のために働いているのか
という信念は、
この日に思い返しておきたいですね。