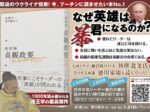- Home
- できる人研究所, 仕事ができる人の歴史入門
- どんな人物だったのだろう「藤原道長」の真実
どんな人物だったのだろう「藤原道長」の真実
- 2024/12/16
- できる人研究所, 仕事ができる人の歴史入門

15日の日曜、大河ドラマ
『光る君へ』が終わりましたね。
というか最後あれ、
ターミネーターの1作ですよね(笑)
紫式部がサラ・コナーにも見えてしまった。
そういえばちょっと吉高由里子さんって、
リンダ・ハミルトンっぽいか?
ともあれ、時代の変化を
予測させて終わったラスト。
史実では藤原道長が亡くなったのは1028年。
紫式部はその3年後に亡くなっているそうですが、
東国で平忠常の乱が始まったのは同じ年。
とはいえ平氏が台頭し、武士の時代になるまでは、
まだ1世紀の期間がありますが、
確かに道長の死後から乱世になっていったのは
事実であるようです。
そう考えると、平将門の乱が起こったのは
935年。
道長は995年から左大臣になって
実権を握っていたのですが、
自身の権力拡大にばかりに力を注いだようで、
実際はほとんど
彼の時代に大きな内乱は起こっていないんですね。
むしろ、そんな平和な時代だったから、
権力闘争に明け暮れたのか……。
かつて学校で歴史を学んだころ、
藤原道長は、権力欲の権化のように
描かれていましたよね。
だいたい、あんな格好いい人物で描かれることなんて
ほとんどなかったのではないか。
60代で亡くなった死因も、
平安時代にして「糖尿病」ですし。
娘たちを利用し、次々と天皇に輿入れさせた功罪は、
最後の哀しい後悔につながっていました。
にしても、そんな悪く描かれる道長を、
徹底的に「いいヤツ」に描いた
今回の大河ドラマ。
なかなか興味深いものでありました。
実際、この時代に最強の武士として、
妖怪退治の逸話を多く残している
源頼光は、道長の男っぷりに惚れ込んで
彼に仕えたとされます。
意外と彼が日本の国政に目を光らせていたというのは、
本当なのかもしれない。
まあ平安時代というのは、基本、
京都以外の秩序は地方任せ。
「治安を守る」という感覚は貴族にないし、
武力に頼るのをタブーにまでされた。
だから当然ながら、
だんだんと秩序は乱れていきます。
そんな中で一時期の平和を築いたのが、
藤原道長で、平和だからこそ生まれた
王朝文学です。
もう少しこの時代のことを
知りたいと思うようにはなりましたね。