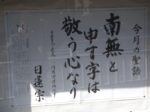「明け団子」の仕事術
- 2025/3/24
- できる人研究所

残り3つになっていますが、
画像はいただいた「明け団子」。
お彼岸の終わり、23日ごろに飾られる、
基本的には「白い団子」ですね。
「何の味もついていない、真っ白な団子」が基本ですが、
スーパーなどでは不評なのか、
あまり売っていません。
だから普通の団子で代用していましたが、
今回はいただきもの。
味がついていなかったり、串に付けたりしないのも
ちゃんとした理由があるんです。
そもそも「お彼岸」って、
どういう時期なのか、ご存知でしたでしょうか?
春分の日と秋分の日、真東から太陽が昇り、
真西に沈む。
そこで西の果てにある「死者の世界=お彼岸」と
現世の世界がつながると、
古くから日本では考えられてきました
するとこの期間は、向こうの世界から死者が、
懐かしい人に会うために
戻ってきたりするわけです。
だからお盆の人同様に、
春分の日もお墓参りが行なわれます。
そこでお彼岸の入りには、
「ぼた餅」(おはぎではない)や
五目ごはん供えられますが、
こちらは季節の「牡丹」に見立てたお菓子で、
死者の魂を迎えるため。
この世で食べてもらうものです。
一方で「明け団子」というのは、
死者の魂に「彼岸」へ持って帰っていただく
「お土産」に当たるものの。
向こうに規制があるのかしれませんが、
あの世で歓迎されないから、
余計な味はつけないのが普通。
さらに丸い団子なのは、
肉体を持たない魂が、団子を転がして持って帰るため
……なんて言われています。
ちょっとコロコロ転がして帰る様子は、
不思議なものがありますが。
なお団子の個数は決まっていないのですが、
かつては「六道輪廻」を象徴して
6つ供られたとか。
「人の魂は6つの世界を彷徨う」
という伝承からですが、
「最後に極楽浄土へ行くことが約束されるべき」
ということで、
これに7つ目が加わり、以後は
「できるだけたくさん供よう」という
話にはなっているようです。
ともあれ、お彼岸が明けたら、
いよいよ春です。
これからはあたたかくなることを
期待したいですね。