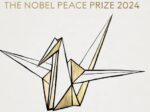- Home
- できる人研究所, 仕事ができる人の歴史入門
- 「八百屋お七」の伝説とは?
「八百屋お七」の伝説とは?
- 2025/3/29
- できる人研究所, 仕事ができる人の歴史入門

日本全国で山火事や
火事の被害が続いている現在ですが、
今、早朝の東京では雨が降っています。
くすぶった炎を雨が完全に消火し、
危険が早く去ってくれるといいですね。
この時期、火事が日本人の悩み事になっていたのは、
ずっと昔の頃から。
というのも、3月29日は
「八百屋お七の日」とされているようです。
旧暦では4月になりますが、
1683年に今の駒込で放火事件を起こした
八百屋の娘「お七」が、火刑によって処刑。
のちに彼女の話は、井原西鶴が
『好色五人女』という作品に記し、
浄瑠璃や歌舞伎で広く伝承されることとなりました。
じつは、史実というのは、
本当のところあまりよくわかっていないようです。
確かに放火犯の女性の記録は残っているようですが、
「お七」という女性も、
八百屋の娘だったかも、よくはわからない。
だから西鶴さんの記録が頼りなのですが、
この悲劇は、愚かな行為をした少女の
たわいもない物語です。
その前の年の年末に
「明和の大火」という大きな火事があり、
お七は焼け出され、吉祥寺というお寺で
しばらく避難生活をすることになります。
このとき、16歳だった彼女は、
お寺の小坊主さんに恋をしてしまうわけです。
やがて家が再建され、お七は八百屋に戻っていく。
修行中の小坊主さんとは、
それっきり会えなくなりますが、
彼女は会いたくて会いたくて仕方がない……。
そこで「もう1度、火事が起これば、
会うことができるのではないか……」と、
彼女は家に放火をしてしまったわけです。
被害は少なかったのですが、
ちょっとした火災でも大損害が起こるくらい
住居の密集する江戸は、火事を恐れていました。
だから放火は、ほんの出来心でも死刑になるくらい
重罪とされていたわけです。
16歳という若さを考慮し、
なんとか減刑しようと奔走した役人もいたのですが、
厳罰の対象にはなりませんでした。
といって、実際のところはわからないのですが、
現代でも同じように。
火災はときに、本人がどんなに気をつけ、
どんなに正直に生きていても
理不尽に人の命や人の資産を奪っていくわけです。
そんな理不尽が、江戸では日常茶飯事に
起こっていたことも事実。
16歳の少女の悲劇は、ある種その理不尽さを代弁し、
軽率な行動を諌めるとともに、
用心をうながすための教訓として
長く語り継がれることになったのでしょうね。