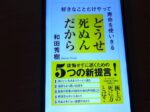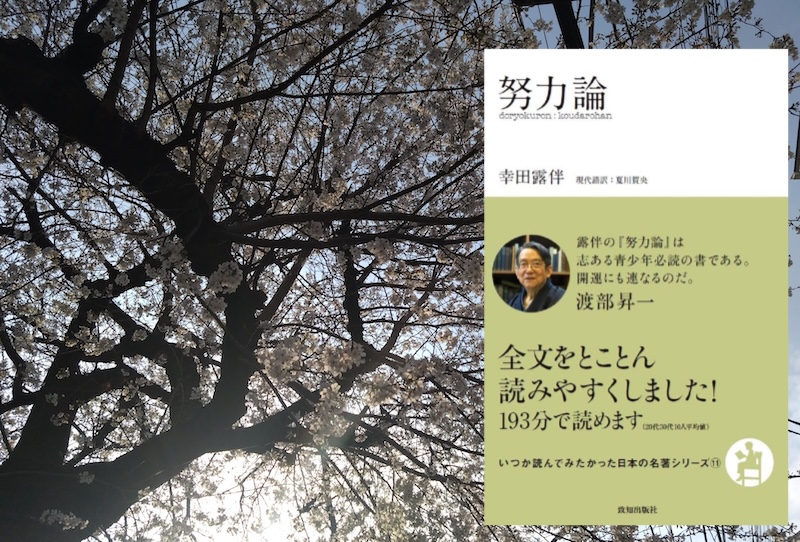
もうすぐ4月、桜の季節ということで、
毎年、私は自分が現代語訳した2冊の古典について
語らせていただいています。
その1冊目はといえば、幸田露伴さんの
『努力論』ですね。
『努力論』はよく誤解されるのですが、
「努力しなさい」なんていう、
精神論を述べた本ではありません。
努力とは、本来、
自分で「努力している」なんていう意識をせず、
「気づいたら楽しみながら
120パーセントの力を出していた」なんていう、
人間が自然な状態で発揮したときに
一番成果が上がります。
そのための「効率的な努力の方法」、
あるいは「楽しい努力の方法」を提示した
明治時代の啓発書が
『努力論』だったわけです。
そんな「楽しい努力法」の1つは、
「春の到来に合わせて、何かやりたいことを
頑張ってみる」ということ。
幸田露伴さんによれば、
人間も自然とともにある生物である以上、
最も心や体のエネルギーが活発になるときに
思う存分、体を活性化させたほうがいい。
それが春だ!……というのは、
春は「張る」という言葉から、
命名された季節だというのが露伴さんの説です。
桜の花が開花し、
虫や小動物が動き出す時期に
人間のエネルギーも最も力強く
「張った」状態になる。
だからこそ、新しいことを春のシーズンに合わせ、
普段よりもずっと効果が出るこの時期に
スタートダッシュをしていこうよ……と
幸田露伴さんは述べているんですね。
実際、新年度が始まり、
仕事でも学業でも、
4月は新しい「こと始め」の時期です。
大谷選手のドジャーズは
開幕から5連勝とすごいことになっていますが、
私たちも春に合わせて
上手に楽しい「努力」をしていきたいものです。
この季節に紹介したい、もう1つの古典は
もちろん桜の花に日本人の精神を象徴させる
『武士道』ですが、
その話はまた、後日にしましょう!