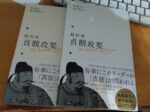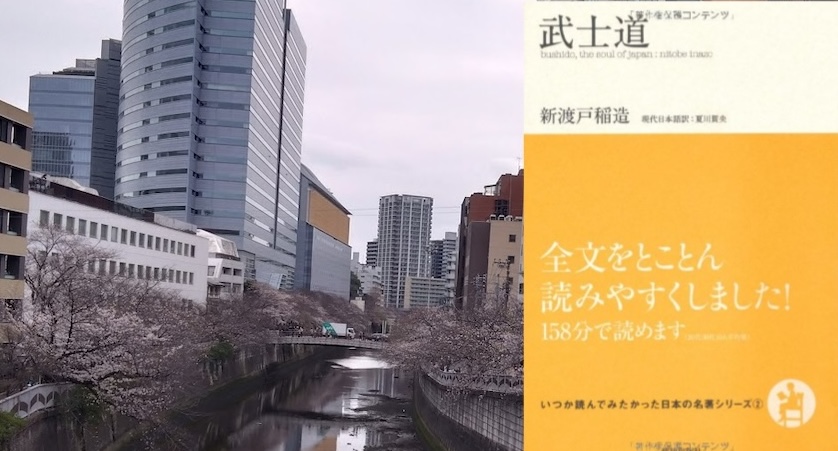
4月になりました。
3月の末、目黒駅の銀行へ行ったついで、
目黒川まで行ってみると、
もう外国人の観光客さんで一杯でした。
いまはどこの桜の名所も、そんな具合ではないか。
よくも悪くも、
日本の桜は国際的になったものです。
ただ、最初の画像は五反田方向、
こちらは中目黒方向ですが、
まだ、あまり咲いていないですよね。

とくに東京に住む方は、
急ぐこともないのではないか……。
寒いし、今は天気もよくないですからね。
そんな桜への言葉として、新渡戸稲造さんの言葉。
「『武士道』は、
我が国の桜と同じものです……」とは、
私が現代語訳した『武士道』の第1章、
出だしの言葉。
まさに「武士道」の本のオープニングです。
どうして「桜=武士道」なのか?
それは、わざわざ桜を見に行くまでもない。
春になれば、私たちはどこでも
桜が咲いている光景を目にします。
たとえずっと家に閉じこもっていたとしても、
窓を見れば、この時期、
枠に花びらが付いていたりする。
家に帰り、上着を見れば、見た記憶がなくても、
桜の花びらがくっついている。
そして何より「香り」ですよね。
いつでもどこでも、
私たちは桜の香りを思い出すことができる。
記憶から一生懸命に消そうとしたって、
日本人であれば、潜在意識の奥底のどこかに
桜のイメージを携えているだろうと
新渡戸稲造さんは考えているわけです。
当人、長く海外に住んでいた経験からも
そう感じていたのでしょうね。
そして「武士道」も、同じものではないかと
新渡戸さんは考えました。
「武士道」が日本人独特の価値観で、
困難に直面したときや、
何かを覚悟をもって行なわねばならないとき、
私たちはいつでも
潜在意識の奥底にある「武士道」を
桜のイメージのように引き出すことができる……。
それがどんなものかは、ぜひ本書……をですが、
「桜」と「武士道」はぜひ、
同義のものと皆に認識してほしいですね(笑)
毎年、そう書いている私は、
切っても切り離せなくなっていますね。